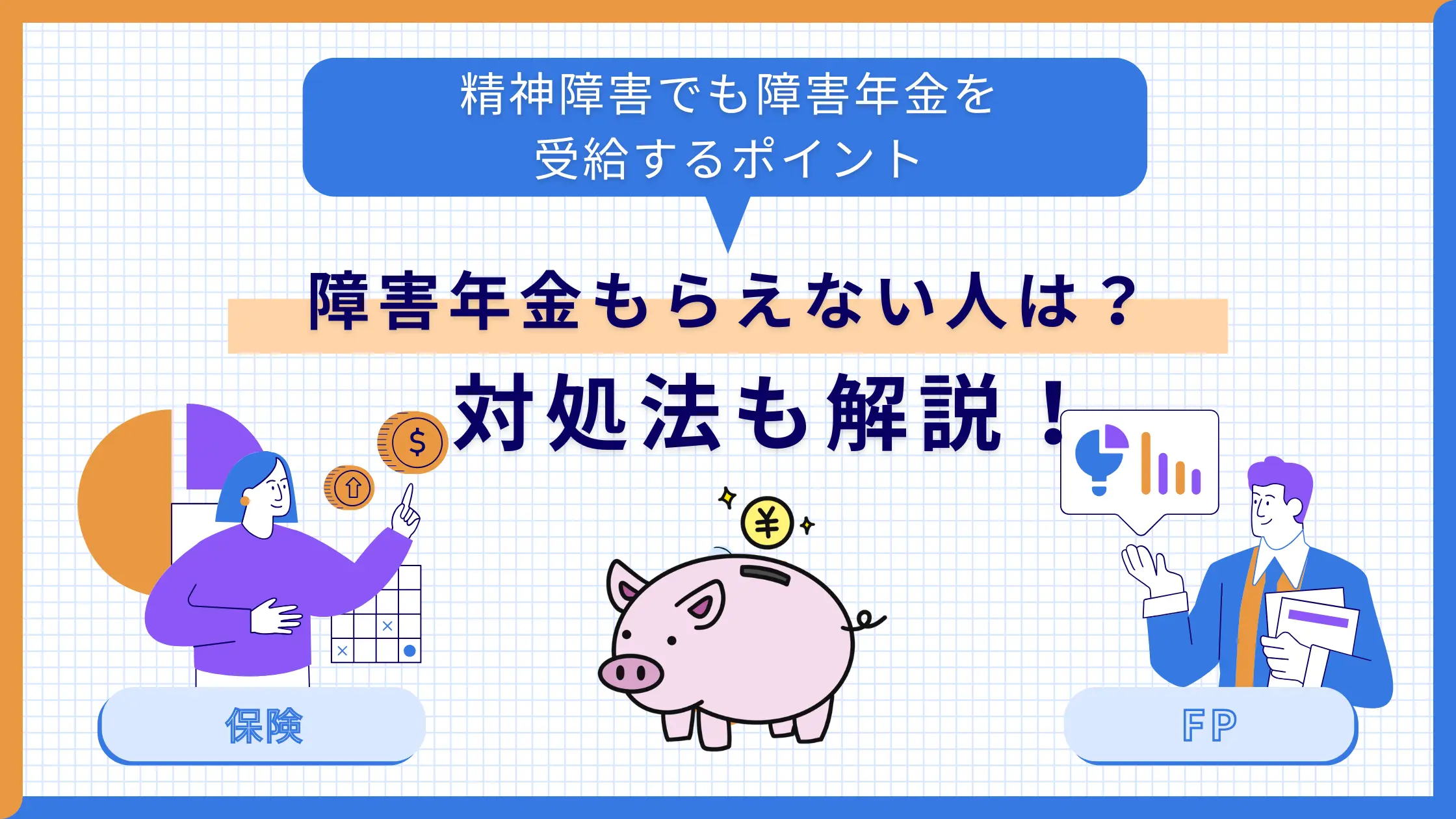この記事では、障害年金がもらえない人の特徴や、精神疾患でも受給できるためのポイントについて詳しく解説します。
結論から言うと、精神疾患でも症状の伝え方や書類の作成次第で障害年金を受給できる可能性は十分にあります。
実際に申請が通らなかった人の多くは、
- 診断書の記載不足
- 初診日
- 納付要件の誤認
など、制度への理解不足が原因です。
詳しく内容を知りたい方はこの記事をチェックしてみてください。
障害年金がもらえない人の共通する特徴とは

障害年金は、一定の要件を満たしていなければ受給することができません。
特に精神疾患においては、見た目ではわかりづらい症状のため、適切に伝えられなかったり、誤解されたりするケースも多くあります。
ここでは、障害年金をもらえない人に共通する3つの特徴を解説します。
※以下の項目をクリックすると、それぞれの詳細に飛びます。
以下で順番に解説します。
①障害年金の受給要件を満たしていないケース
障害年金を受けるには
- 初診日要件
- 保険料納付要件
- 障害状態要件
の3つを満たす必要があります。
- 初診日が曖昧で証明できない
- 保険料の未納が続いている
- 障害認定日における状態が等級に達していない
など、いずれかの要件を満たしていないと、たとえ症状が重くても不支給になります。
特に20歳前後の未納や初診日の曖昧さは注意が必要です。
②障害認定基準を正しく理解していないケース
認定基準に対する誤解が原因で「自分は対象外だ」と思い込み、申請をあきらめる人も少なくありません。
実際には、認定基準は症状の重さだけでなく、日常生活への支障や介助の必要性を総合的に判断されます。
たとえ軽度に見える精神疾患でも、日常生活に大きな影響があれば受給対象になることもあります。
③申請時に情報の伝え方を間違えている
申請書や診断書で実際の症状をうまく伝えられていないことも、不支給の大きな要因です。
医師に伝える内容が不十分だったり、病歴・就労状況申立書に具体性がなかったりすると、審査側に正確に伝わりません。
特に精神疾患は主観的な訴えが中心になるため、書き方や伝え方次第で評価が大きく変わる可能性があります。
障害年金を精神疾患で申請しても通らない理由
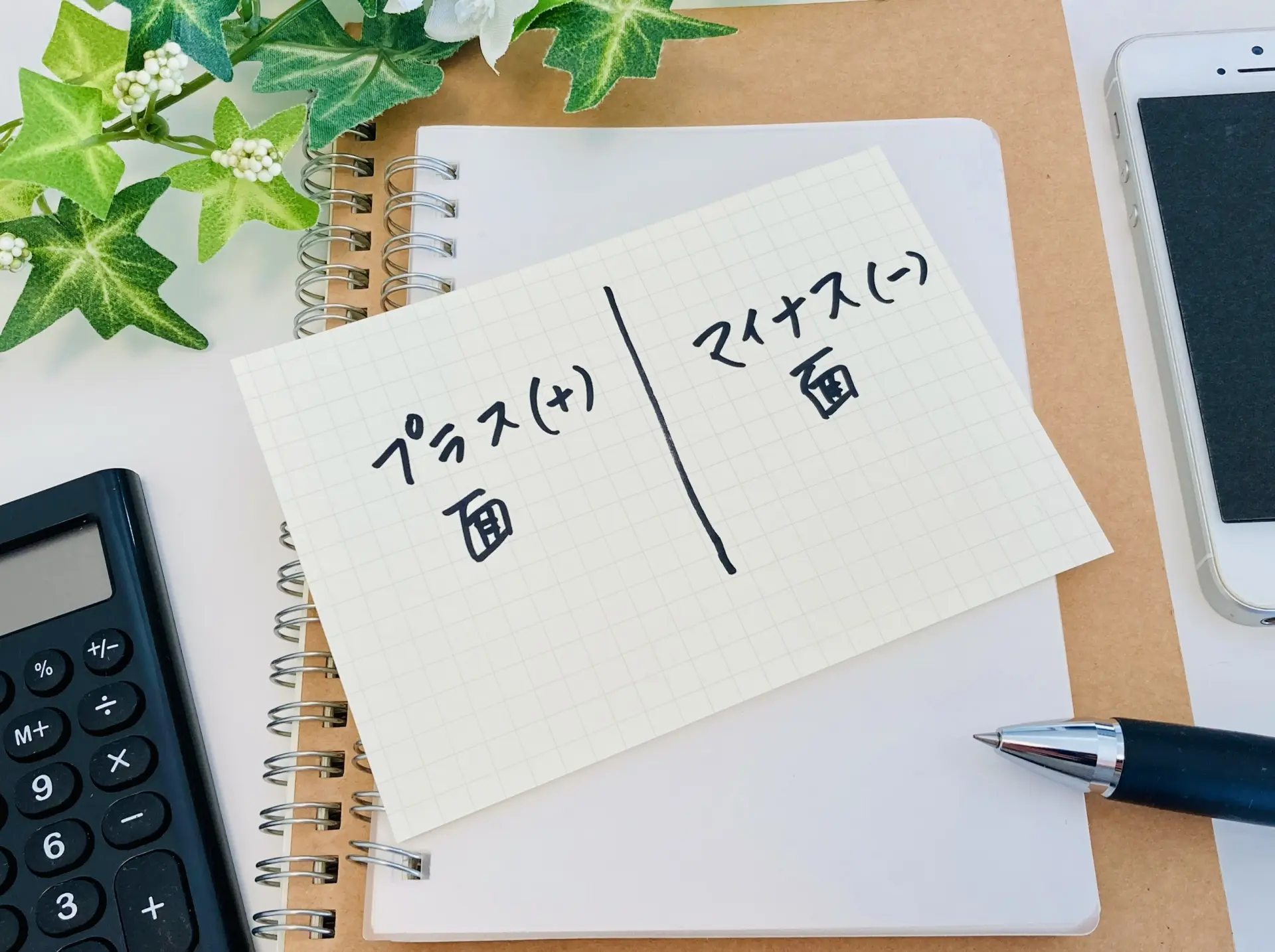
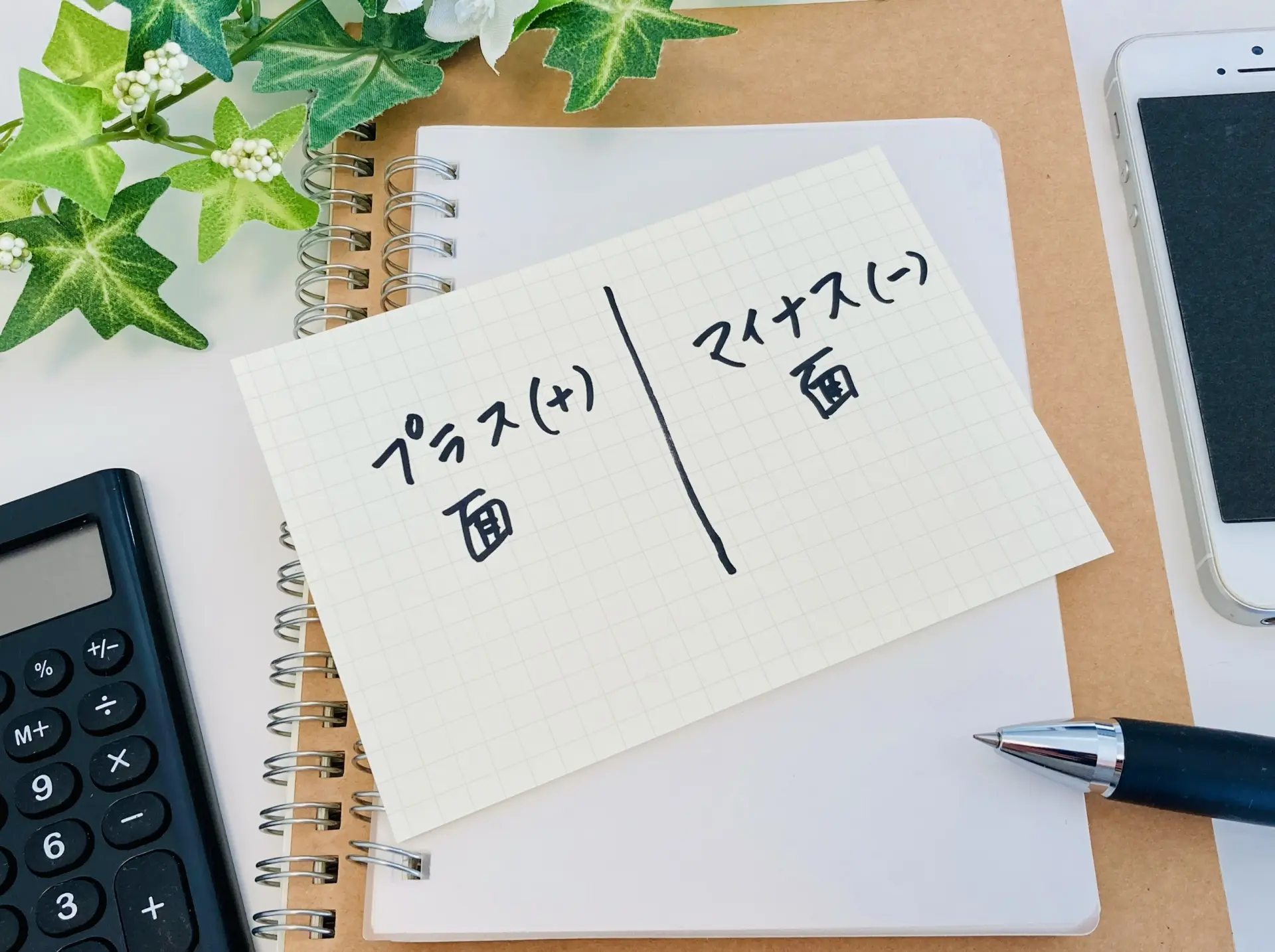
精神疾患で障害年金を申請しても、想定外の理由で不支給になることがあります。
見た目に現れにくい病気のため、実際の生活困難さが審査に反映されにくいのが原因のひとつです。
ここでは、精神疾患で通らない主な理由を3つの観点から詳しく解説します。
※以下の項目をクリックすると、それぞれの詳細に飛びます。
以下で順番に解説します。
①診断書と実際の症状にギャップがある
障害年金の審査では、医師が作成する診断書が最重要書類です。
ところが、この診断書に記載されている内容が、実際の症状や生活状況と一致していないと、審査で正しく評価されません。
例えば、
- 日常生活で困っていることがうまく反映されていない場合
- 症状の深刻さが軽く見積もられている場合
などは、不支給の原因になります。
②就労状況や生活状況が誤解を招く
精神疾患を抱えながらも、短時間の仕事や軽作業をしている人は少なくありません。
しかし、審査側が「普通に働けている」と判断すると、「日常生活に著しい支障がない」と見なされ、障害等級に該当しないとされることがあります。
また、一人暮らしをしていること自体も「自立できている」と判断されやすいため注意が必要です。
③精神疾患に対する認定基準の曖昧さ
精神疾患は外見では分かりづらく、定量的な判断が難しいため、障害等級の認定にばらつきが出やすい傾向にあります。
さらに、神経症や軽度のうつ病などは「原則対象外」とされることもあり、正確な症状や支援の必要性を診断書に明記しないと、審査側に深刻さが伝わらないまま不支給となることもあります。
主治医が書く診断書に障害の状態を正確に反映してもらうためのツールを作成しました。私はこれを活用して10年分の障害年金トータルで2,200万円を勝ち取りました。ぜひご活用ください。
精神疾患で障害年金が不支給になる典型的なケース


精神疾患による障害年金の申請は、外見で判断されにくいこともあり、審査で不利になることがあります。
中でも「不支給」になるパターンには一定の傾向があります。
ここでは、精神疾患を抱えながらも障害年金が通らなかった代表的なケースを3つ紹介します。
※以下の項目をクリックすると、それぞれの詳細に飛びます。
以下で順番に解説します。
①軽症と見なされる神経症単独の場合
神経症(不安障害やパニック障害など)の場合、障害年金の認定基準では「原則として認定の対象とならない」とされています。
ただし、うつ病や統合失調症などの精神病性障害と併発している場合には、重症度によって認定の可能性があります。
神経症単独では受給が難しいため、診断名や併発の有無の確認が重要です。
②一人暮らしや就労で「日常生活に支障なし」と判断された場合
精神疾患の状態が重くても、
- 一人暮らしができている
- 週数回でも働いている
などの場合、審査側に「日常生活に著しい支障がない」と判断されてしまうことがあります。
実際にはサポートがあって成り立っている生活であっても、客観的に補足説明がないと、「自立している」と受け取られてしまうことがあるため要注意です。
③初診日や保険料納付に問題があるケース
障害年金の支給には
- 初診日の証明
- 保険料納付状況
が大前提です。
特に精神疾患では、初診日が古かったり、複数の病院を受診していることで、初診日が特定できないケースがあります。
また、20歳前後の保険料未納や免除申請をしていなかった場合、納付要件を満たせずに支給対象外となることも多くあります。
障害年金がもらえない病気と該当する精神疾患の違い


障害年金の申請において、「どの病気が対象になるのか?」という点は非常に重要です。精神疾患の中には、原則として認定の対象外とされるものもあり、症状の重さだけでは判断できません。ここでは、障害年金がもらえないとされる病気と、実際に該当する精神疾患の違いについて解説します。
※以下の項目をクリックすると、それぞれの詳細に飛びます。
以下で順番に解説します。
①障害年金の対象外とされやすい精神疾患とは
障害年金では「神経症」単独の診断、例えば以下のように
- パニック障害
- 適応障害
- 不安神経症
などは原則として対象外とされています。
これらは、症状が一定の範囲でコントロール可能とされ、日常生活の制限が軽度と判断されやすいためです。
診断書においても「神経症」と記載されると、それだけで不支給となる可能性が高くなります。
②受給対象になりやすい精神疾患の特徴
- うつ病
- 統合失調症
- 双極性障害
などの「精神病性障害」は、障害年金の受給対象として認定されやすい疾患です。
これらの病気では、日常生活や就労において著しい制限が生じやすく、他者からの援助が必要なケースも多くみられます。
診断書に「精神病性障害」として明記されていれば、審査においても受給の可能性が高くなります。
③併発によって対象になるケースの例
神経症とされる病気でも、うつ病や発達障害など他の精神疾患と併発している場合には、障害年金の対象になる可能性があります。
たとえば
- パニック障害+うつ病
- 適応障害+発達障害
などのように複数の診断があり、日常生活への影響が重度である場合、診断書の記載内容次第では審査を通過できることがあります。
併発疾患の記載と症状の説明が鍵となります。
年金未納が障害年金の不支給に与える影響とは


障害年金は、病気や障害の状態だけでなく、保険料の納付状況も審査対象となります。
中でも「未納」は、たとえ重い障害があっても不支給となる原因の一つです。
ここでは、年金の未納がどのように障害年金の可否に影響するのかを詳しく解説します。
※以下の項目をクリックすると、それぞれの詳細に飛びます。
以下で順番に解説します。
①保険料納付要件を満たさない場合のリスク
障害年金の支給には、原則として「初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上が納付または免除されていること」が必要です。
この要件を満たしていないと、障害の重さに関係なく支給対象外となります。
また、直近1年間に未納がなければよいとされる特例もありますが、いずれにしても「未納」は不支給の大きな要因です。
②未納と免除の違いと障害年金への影響
「未納」と「免除」は似て非なるものです。
保険料の免除申請をしていれば、納付していなくても納付期間としてカウントされ、支給要件を満たせる場合があります。
一方、未納は放置していた状態を指し、まったく考慮されません。
経済的に苦しい場合でも、免除や猶予制度を活用することで、将来的な障害年金の受給資格を保てます。
③救済措置が適用される特例ケース
納付要件を満たしていない場合でも、「直近1年間に未納がなければOK」という特例(平成38年3月31日まで適用)があります。
この特例に該当すれば、納付率が3分の2未満でも障害年金の申請が可能です。
また、初診日が20歳前の場合は納付要件自体が不要です。
自分がどのパターンに該当するかを確認することで、救済の可能性を探ることができます。
発達障害で障害年金をもらえない人の実例と対策


発達障害を抱える方の中には、日常生活に大きな困難を抱えているにも関わらず、障害年金の審査で不支給とされるケースが少なくありません。
ここでは、発達障害で障害年金をもらえなかった実例と、その対策について詳しく解説します。
※以下の項目をクリックすると、それぞれの詳細に飛びます。
以下で順番に解説します。
①発達障害で不支給となった典型的な事例
たとえば、ASD(自閉スペクトラム症)と診断されながらも、
- 一人暮らしをしている
- 短時間勤務が可能である
と判断された場合、「生活に重大な支障がない」と見なされ不支給になることがあります。
また、診断書の記載があいまいで、支援の必要性が十分に伝わっていないケースも不支給の原因となります。
②発達障害でも認定されるためのポイントとは
発達障害で障害年金を受給するためには、診断書に具体的な支援状況や生活の困難さを明記してもらうことが重要です。
たとえば、
- 指示がなければ家事ができない
- 人との関係を築くのが極めて困難、同じミスを繰り返して仕事に支障がある
など、実生活に即した内容を盛り込むことで、審査員に実態が伝わりやすくなります。
③診断名と生活実態の伝え方が審査のカギ
診断名だけでなく、生活実態との一貫性が非常に重要です。
たとえば「軽度の知的障害」や「ADHD」の診断があっても、診断書に書かれている生活能力が高く評価されていれば不支給になります。
年齢によって障害年金がもらえないケースとその例外


障害年金は「何歳でも申請できる制度」と思われがちですが、実は年齢によって申請できないケースがあります。
特に精神疾患を抱える方は、申請のタイミングを逃すことで受給できなくなる場合もあるため、制度上の年齢制限を理解しておくことが大切です。
※以下の項目をクリックすると、それぞれの詳細に飛びます。
以下で順番に解説します。
①原則65歳を超えると障害年金は申請不可
障害年金の新規申請は、原則として65歳までに行う必要があります。
- 65歳を超えてから初めて医師の診断を受けた場合
- 65歳を過ぎて申請しようとした場合
は、制度上申請そのものができなくなるため注意が必要です。
高齢になってからの発症であっても、年齢制限の壁があることを理解しておくことが重要です。
②20歳未満や高齢者の例外的な受給ケース
一方で、20歳未満で発症した先天性の障害や知的障害の場合、「20歳前障害」として保険料の納付要件なしで申請が可能です。
また、65歳を過ぎていても、障害認定日が65歳以前であれば、事後的に申請することが認められるケースもあります。
つまり、発症・初診が65歳未満であることがカギとなります。
③年齢による制限を受けないために注意すべき点
年齢による制限を受けないためには、障害の発症や診断があった時点で早めに動くことが大切です。
精神疾患の場合、症状の進行や再発によって判断が遅れることも多いため、
- 65歳までに初診日があるかどうかを記録しておくこと
- 保険料の納付状況を確認しておくこと
などが、受給資格の確保につながります。
精神疾患で障害年金をもらえない場合の対処法


精神疾患で障害年金の申請をしたものの不支給となった場合、諦める前にできる対処法があります。
審査で不利になりやすい精神疾患こそ、伝え方と準備の仕方が重要です。
ここでは、不支給を受けた後に実践できる具体的な対応策を解説します。
※以下の項目をクリックすると、それぞれの詳細に飛びます。
以下で順番に解説します。
①申請内容を見直して再請求する方法
障害年金が不支給となっても、症状に変化があれば「事後重症」として再請求が可能です。
また、初回申請時に書類の不備や説明不足があった場合、内容を修正して再提出することで支給につながるケースもあります。
再請求には前回の申請書類の内容を精査し、どこが不足していたのかを明確にすることが重要です。
②診断書や病歴・就労状況申立書の改善ポイント
不支給となる大きな理由のひとつが「診断書の内容不足」です。
日常生活の支障や就労制限など、実態に即した情報が反映されていなければ、正しい判断はされません。
また、病歴・就労状況等申立書では、家族からの支援状況や職場での配慮など、生活の困難さを具体的に説明する必要があります。
内容が抽象的だと審査に不利になります。
③社会保険労務士など専門家への相談が有効な理由
精神疾患の申請は、制度の仕組みを理解していても、表現や説明の仕方ひとつで結果が大きく変わる分野です。
障害年金に詳しい社会保険労務士に相談することで、自分では見落としていた改善点に気づける可能性が高まります。
また、過去の成功事例を参考に申請の精度を高めることもでき、結果的に受給できる可能性が大きく上がります。
精神障害で障害年金がもらえない人に関連したQ&A


精神障害で障害年金がもらえない人に関連してよくある質問は以下のとおりです。
精神障害で障害年金をもらえない人:まとめ


障害年金がもらえない人の特徴や精神疾患でも受給できるポイントについて解説してきました。
診断書の内容や申請書類の書き方を見直すだけで、受給できる可能性は大きく変わります。
日常生活に支障がある方は、あきらめずに正しい手続きを進めることが重要です。
障害年金の詳細や申請を成功させたい方は、今すぐ以下のツールをチェックしてみてください。
主治医が書く診断書に障害の状態を正確に反映してもらうためのツールを作成しました。私はこれを活用して10年分の障害年金トータルで2,200万円を勝ち取りました。これさえあれば社労士に何十万と支払う必要はありません。ぜひご活用ください。