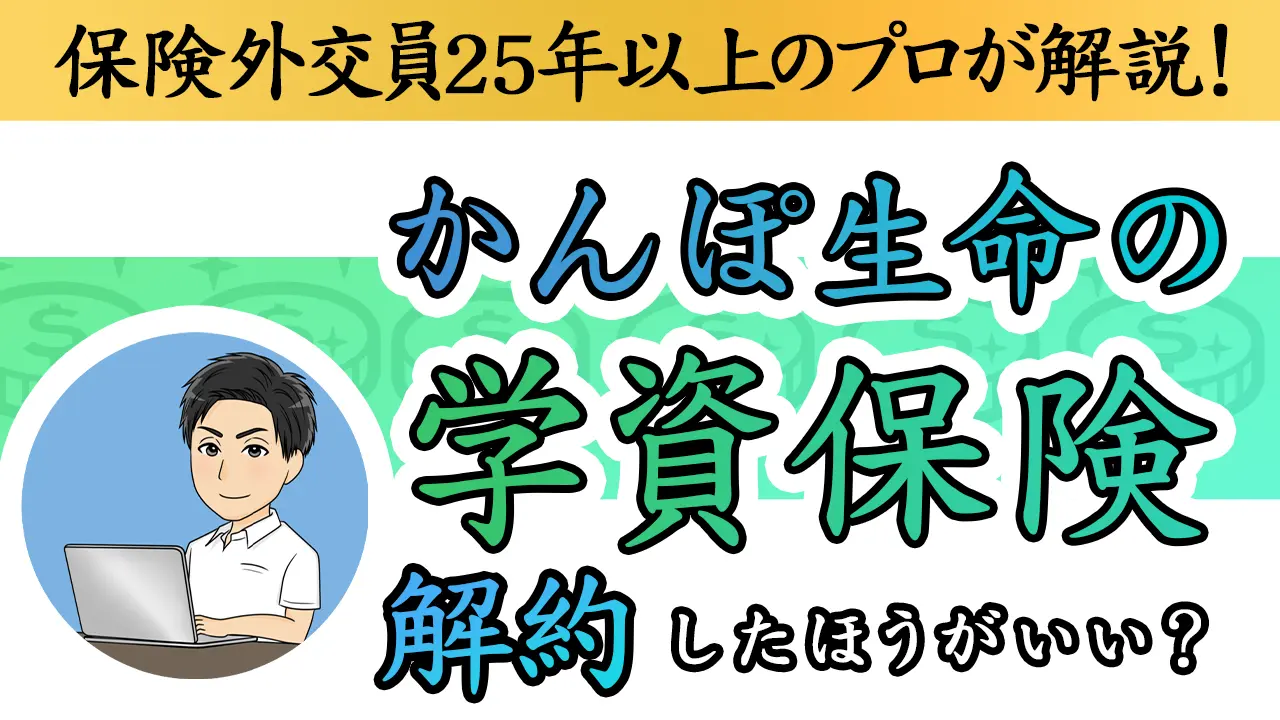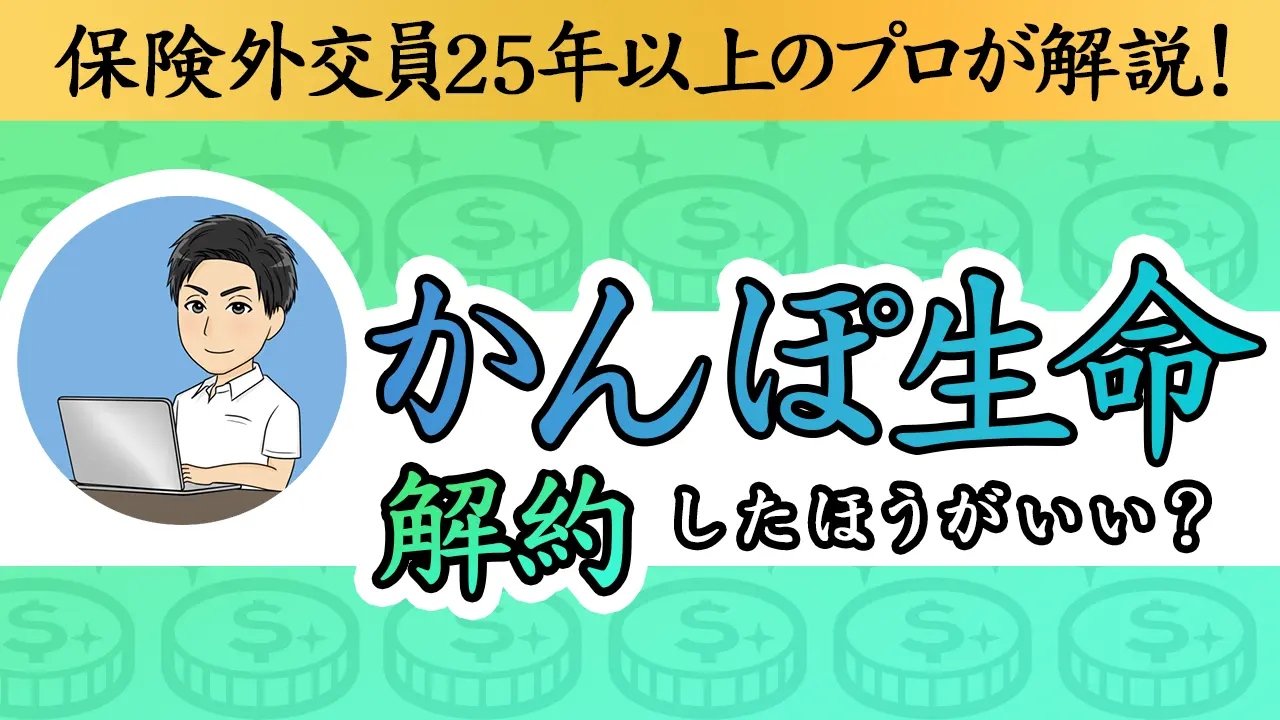「このまま続けても、大丈夫なのかな…」
かんぽ生命の学資保険を契約しているパパママの中には、そんな不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
契約当時は「子どもの将来のため」と思って入ったはずなのに、最近になって「元本割れするらしい」「ほかの運用のほうが得って聞いた」といった情報を目にして、不安になった——そんな声も少なくありません。
この記事では、「かんぽ生命の学資保険は解約した方がいいのか?」という疑問に対して、
- 解約が向いているケース
- 解約しないほうが安心な人
- 解約タイミングや返戻金の目安
などをわかりやすく解説していきます。
「何が正解かわからない」「誰かに背中を押してほしい」
そんなあなたが、自分にとってベストな選択ができるように。
本記事が、小さな一歩を踏み出すヒントになれば幸いです。
かんぽ生命の学資保険は解約した方がいい?(結論)

結論からお伝えすると、かんぽ生命の学資保険は、人によっては解約した方がいい場合があります。
でも、それは「この保険がダメだから」という話ではなく、「今のあなたの生活や目的に合っているか」が大切なんです。
たとえば、毎月の保険料が家計を圧迫していたり、「元本割れするかもしれない」と不安を感じている場合は、一度立ち止まって見直すチャンスかもしれません。実際、「解約してつみたてNISAなどに切り替えた」「その分を貯金にまわした」という人も増えてきています。
一方で、「強制的に積み立てできるから安心」「子どもが病気がちで保障を残しておきたい」など、保険に“安心感”を求めている方には、無理に解約しない方がいいケースもあります。
大切なのは、「本当に今の保険が自分たちの暮らしに合っているか?」を、もう一度じっくり見直してみること。誰かの正解ではなく、「わが家にとっての正解」を見つけましょう。
かんぽ生命の学資保険は解約した方がいいと言われている理由5つ
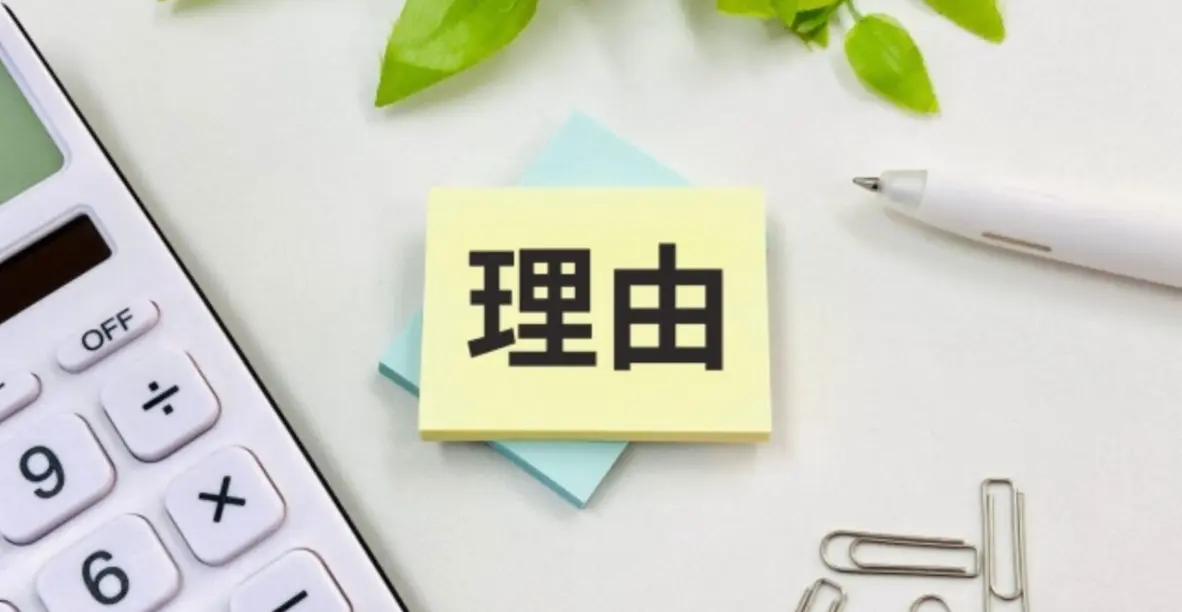
「本当に今の保険が、自分たちの暮らしに合っているかどうか」さきほど、そうした視点が大切だとお伝えしました。
では、実際になぜ「かんぽ生命の学資保険は解約した方がいい」と言われるのか? その理由を具体的に知っておきたいと思いませんか?
ここでは、解約をすすめる声が多い5つの理由を具体的に紹介していきます。
これを知ることで、自分にとって「本当に見直すべきタイミングなのか?」が、きっと見えてくるはずです。
①元本割れする可能性が高いから
かんぽ生命の学資保険は、契約の時期やプランによっては、払ったお金よりも戻ってくるお金の方が少なくなること(=元本割れ)があります。
とくに「はじめのかんぽ」は、最近の金利の低下や制度改定の影響で、返戻率が100%を下回るケースが増えているんです。昔は「保険に入っておけば安心だし、少しは増える」と思われていた時代もありましたが、今は金利がとても低いため、「貯金と変わらないどころか、減ってしまう」場合も。それに気づいて「このままでいいのかな?」と心配になるのは当然ですよね。
ネットでも「想像より少なかった」「これなら貯金の方がよかった」といった後悔の声が目立ちます。せっかく何年も積み立てたのに、戻ってくるお金が少ないと、がっかりしてしまいますよね。
教育資金は、子どもの将来にかかわる大切なお金です。だからこそ、「今の保険が本当に家族に合っているか?」を、少し立ち止まって見直すことが、安心への第一歩になるはずです。
②保険相談で解約した方がいいと言われたから
保険の相談窓口やファイナンシャルプランナー(FP)に相談したとき、「この保険は今の時代には合わないかもしれません」と言われた方もいると思います。
その理由は、保険料に対して返ってくるお金が少なかったり、保障の内容がかたよっていたりするからです。
とくに、返戻率が下がっている今の保険では「積み立てのメリットが薄い」と指摘されることもあり、「これなら他の方法の方がいいですよ」と提案されることもよくあります。最近では、つみたてNISAや投資信託など、もっと柔軟で効率的な方法を選ぶ家庭も増えてきました。
実際に相談を受けた方からは、「話を聞いて納得できた」「やっぱり不安だったから、決断できてよかった」という声もあります。専門家の意見は、誰かの押しつけではなく、“冷静な判断の材料”として役立つもの。
「迷っていたけど、話を聞いてスッキリした」そんなきっかけになることもあるので、不安を抱えている方は、一度相談してみるのもよいかもしれません。
③金利の高い商品が他にもあるから
最近では、学資保険よりも「もっとお金が増えるかもしれない方法」として、つみたてNISAや投資信託を使う人が増えています。これらは元本保証があるわけではありませんが、長い目で見れば、学資保険より多くのリターンが期待できることもあります。
たとえば、つみたてNISAでは年間40万円までの投資が非課税ででき、 投資信託をコツコツと積み立てることで、時間を味方につけてお金を育てることができます。リスクはあるものの、きちんと仕組みを理解して活用すれば、将来の教育資金をより効率よく準備できるというメリットがあります。
また、学資保険と違って、途中で金額を変更したり、運用先を変えたりといった柔軟性があるのもポイントです。これまで「保険が一番安全」と思っていた方でも、「思っていたより学資保険って固いだけで増えない」と感じ、運用型の商品に興味を持つようになっています。
「10年以上先の話だからこそ、今から育てておきたい」そんな気持ちを持つ方には、学資保険以外の選択肢を知っておくことがとても大切です。
④教育資金を準備する方法は他にもあるから
教育資金を準備するのに、必ずしも学資保険を使わなければいけないわけではありません。
たとえば、定期預金、財形貯蓄、個人向け国債など、リスクをおさえながらお金を貯められる方法はたくさんあります。学資保険は、毎月決まった金額を払って満期まで続けることで受け取るお金が決まる仕組みです。でも、途中で家計が苦しくなっても金額の変更ができなかったり、やめたら戻る金額が減ってしまったりと、柔軟性に欠ける面があります。
その点、他の方法では「今月は少なめに」「急に出費があったから一時ストップ」など、生活スタイルに合わせて自由に貯められるという利点があります。また、いざというときに引き出しやすく、資金の使い道も自分でコントロールできるのは大きな安心です。
「学資保険しか方法がない」と思っていた方も、一歩視野を広げてみると、「うちにはこっちの方が合っているかも」と感じることがあるかもしれません。
⑤ 保障内容が限定的で柔軟性に欠けるから
かんぽ生命の学資保険は「教育資金のための積立」に特化している保険です。そのため、医療保障や死亡保障など、“もしもの時”に備える部分が手薄であることが多いです。
たとえば、お子さんが入院したときの医療費や、親に何かあったときの生活費をまかなう保障は、学資保険ではカバーしきれない場合があります。また、契約後に内容を見直したくても、簡単に変更できないことも不便に感じる人が多いです。
最近では、医療や生活の備えも一緒に考えられる「掛け捨て保険」や「収入保障保険」など、家族全体を守れる保険を選ぶ家庭が増えています。「教育資金だけでなく、万が一にもちゃんと備えておきたい」という声が強まってきたことが背景にあります。
「何を守りたいか」「どんなときに役立ってほしいか」を考えると、今の学資保険だけでは足りないと感じるかもしれません。 家族の安心を本気で考えるからこそ、“教育資金+α”の視点も大切になります。
かんぽ生命の学資保険を解約した方がいい人や状況5選


学資保険はすべての人にとって「必要なもの」とは限りません。 大切なのは「今の暮らしや家計」「将来の計画」に合っているかどうかです。 ここでは、かんぽ生命の学資保険を解約した方がいいかもしれないと考えられる具体的なケースを5つ紹介します。
①保険料が家計を圧迫している場合
毎月の保険料が家計にとって大きな負担になっている場合は、無理に続けるよりも一度見直すことをおすすめします
たとえば、「保険料を払うために毎月ギリギリの生活をしている」「習い事をあきらめた」「旅行や外食も我慢している」など、保険のために生活が苦しくなっていないでしょうか。教育費のために備えることは大切ですが、今の生活のゆとりを奪ってしまっては本末転倒です。子どもと過ごす“今”を大切にすることも、将来への投資といえます。
また、家計に余裕がない状態では、突然の出費や病気などにも対応しづらくなってしまいます。
「保険料が負担だな」「続けるのがつらいな」と感じたら、それは見直しのサインかもしれません。無理して続けるよりも、自分たちの暮らしに合った方法を探してみましょう。
②急に大きな出費ができた場合
突然の出費にどうしても対応しなければならないとき、学資保険の解約も一つの選択肢になります。
たとえば、家の修理、車の買い替え、親の介護、医療費など、大きなお金が必要になる場面はどの家庭にも起こり得ます。「急にまとまったお金が必要になった。でも貯金はあまりない」そんなとき、学資保険に積み立てていたお金を使えたら、助かると感じる方も多いでしょう。
もちろん、解約にはデメリットもあります。すぐに解約すると返戻金が少なかったり、元本割れする場合もあります。ですが、「今、本当に必要なお金」を優先することも立派な判断です。
将来のための備えも大切ですが、今の暮らしを立て直すことが先というケースもあるのです。その時は、再スタートのつもりで、家計や保障を見直してみるのもよいかもしれません。
③他の金融商品で効率的に資産運用を考えている場合
「学資保険より、もっとお金が増える可能性のある方法で教育資金を準備したい」そう考えている方にとっては、保険をやめて資産運用に切り替えるのも一つの有効な手段です。
近年、つみたてNISAや投資信託などを活用して、教育費や老後資金を“育てる”人が増えています。これらは元本保証こそないものの、長期で積み立てれば、学資保険よりも大きなリターンが期待できる場合もあります。もちろんリスクはありますが、仕組みを理解して着実に積み立てていけば、資産を効率的に増やすことができます。とくに、学資保険の返戻率が下がっている今、「同じお金を使うなら、もっと伸びる可能性がある方へ」と考えるのは自然な流れです。
大切なのは、「どちらが正しいか」ではなく、「どちらが自分たちに合っているか」。
より自由に、より賢くお金を使いたい人には、運用への切り替えは魅力的な選択です。
④契約内容がライフプランに合わなくなった場合
「保険を契約したときと、今の暮らしや考え方が変わってきた」そんなとき、保険の見直しはとても大切です。
たとえば、家族が増えた、転職して収入が変わった、進学の方針が変わった、親との同居が始まったなど、ライフプランは時間とともに変化していきます。その中で、「この保険、もううちの状況に合ってないかも…」と感じる瞬間があるかもしれません。最初は良かれと思って入った学資保険でも、今となっては「使いにくい」「返戻金のタイミングが合わない」と感じることもあります。
そんなときは、「もったいないから続ける」ではなく、「今に合った方法に切り替える」という前向きな決断も必要です。保険は契約して終わりではなく、暮らしに合わせて見直していくものです。その変化に気づけたあなたは、すでに“賢い選択”を始めているのかもしれません。
⑤貯金で対応できる人
すでにしっかりと貯金があり、「学資保険に頼らなくても教育費はまかなえそう」という場合、保険をやめるという選択もアリです。
とくに、コツコツと計画的に貯めるのが得意な方や、家計管理がしっかりしているご家庭では、保険に縛られず自由にお金を使える方がメリットが大きいこともあります。学資保険は、途中で内容を変えるのが難しかったり、自由に引き出せなかったりする点で、柔軟性に欠ける部分があります。
一方、貯金であれば、急な出費にもすぐに対応できて、家族のライフスタイルに合わせて使い方も選べます。
「毎月の積立や目的別貯金がきちんとできている」「投資も含めてお金の管理ができている」
そんな人にとっては、保険で縛るよりも自分でコントロールできる形のほうが安心につながるかもしれません。
かんぽ生命の学資保険を解約しない方がいい場合や状況5つ


すべての人にとって「解約が正解」とは限りません。 家族の状況や性格、お金の管理スタイルによっては、学資保険をそのまま続けた方が安心できるというケースもあります。 ここでは、「こんな人・こんな状況なら解約は慎重に考えた方がいい」という代表的な5つのパターンをご紹介します。
①利息よりも安心感を重視する人
「少しでも多く増やす」より、「確実に受け取れるほうがいい」そんな安心感を大切にする人にとって、学資保険はとても頼もしい存在です。
たとえば、契約者(親)に万が一のことがあった場合でも、保険の仕組みによっては、以後の保険料の支払いが免除され、満期には教育資金がちゃんと受け取れるという安心設計になっているものもあります。
これは、普通の貯金や投資商品にはない大きなメリットです。「自分に何かあっても、子どもの進学だけは守りたい」そんな気持ちを持っている方には、解約は慎重に考えた方がよいでしょう。
お金を“増やすこと”よりも、“守ること”に価値を感じるタイプの人には、学資保険のような確実性のある仕組みは、やはり心強いものです。
②貯蓄が苦手な人
「あると使ってしまう」「つい口座から引き出してしまう」そんな方にとって、学資保険は“強制的にお金を貯める仕組み”として効果的です。
学資保険は、毎月決まった額を引き落としで積み立てるため、「知らないうちに貯まっている」という感覚で利用できるのが魅力。「続けるのが得意じゃない」「途中で挫折しがち」というタイプの人でも、仕組みによって自然とお金が積み上がっていきます。
また、途中でお金を引き出すのが簡単ではないぶん、計画通りに教育資金を確保しやすいというメリットもあります。自由に使える貯金だと、気づけば使ってしまっていた…という経験がある方には、この“縛り”がむしろありがたく感じられるはずです。
「自分に甘いタイプかも」と思うなら、無理に解約せず、この仕組みを活かしていくのもひとつの考え方です。
③子どもが病気にかかっている人
もし、今加入している学資保険に医療特約や保障がついている場合は、解約を慎重に検討する必要があります。
子どもが持病を持っていたり、定期的な通院・入院が必要だったりする場合、医療保障がある学資保険はとても心強いもの。一般的な医療保険に入りづらいケースでも、学資保険に付帯している保障でカバーできることがあります。
また、子どもの健康状態によっては、一度解約してしまうと次に保険に入り直せない可能性もあります。将来の入院や手術など、予測できないことに備える意味でも、既存の保障は貴重です。
「今はお金が必要だから」と安易に解約してしまうと、あとで大切な保障を失って後悔することもあるため、
このような場合は専門家に相談しながら慎重に判断することをおすすめします。
④教育資金の受取時期が近い場合
すでに教育資金の受け取りがあと数年以内に迫っているような段階であれば、解約はおすすめできません。なぜなら、学資保険の多くは「満期で受け取ること」を前提とした設計になっているため、途中で解約すると損になるケースが多いからです。
たとえば、あと1〜2年で満期なのに今解約してしまうと、返戻金が満額より少なくなったり、もともと受け取れるはずだった祝い金などがなくなったりすることがあります。
「せっかくここまで頑張って続けてきたのに…」という残念な結果にならないためにも、満期までの期間が短ければ短いほど、「あと少し我慢して受け取る」という判断の方が得になる場合が多いです。一度、解約時と満期時の金額を比較してみてから判断すると、納得感のある選択ができるはずです。
⑤再加入が難しい年齢になっている場合
いったん解約すると、「また入りたくなったときに、同じ条件ではもう入れない」可能性があります。これは、とくに契約者の年齢が上がってきている場合や、健康状態に不安がある人にとって、大きなリスクになります。
たとえば、若い頃に契約したときには保険料が安かったのに、再加入すると年齢が上がっていて保険料が高くなってしまうこともあります。また、健康診断で引っかかってしまうと、新しい保険に入れなかったり、条件が不利になることも。
「今の保険には不満があるけど、じゃあ次に同じような保険に入れるか?」と考えたときに、難しさを感じる場合は、続けておく方が無難という判断も大いにアリです。
将来の自分や家族にとって後悔のない選択ができるように、長い目で見て今の保険の価値を見直してみましょう。
かんぽ生命学資保険の返戻率は?


結論からお伝えすると、かんぽ生命の学資保険「はじめのかんぽ」は、契約内容によっては返戻率が100%を超える場合もありますが、他社と比べると少し控えめな水準になっています。
- これまでに支払った保険料の合計に対して、将来受け取ることができる学資金の割合のことをいいます。
- 計算式はとてもシンプルで、
返戻率(%)=(受取総額 ÷ 払込総額)× 100 - この割合が100%を上回れば「払った分より多く返ってくる」ことになりますし、100%を下回れば「元本割れ」となります。
- 30歳の男性
- 0歳の子どもに対して「はじめのかんぽ」に加入
- 保険料を10歳までに支払い終えた場合、返戻率はおよそ101.2%
- 支払総額197万5,200円に対し、受取額は200万円
参考:はじめのかんぽについて
他社の代表的な学資保険と比べると、
- フコク生命「みらいのつばさ」:109.5%
- JA共済「学資応援隊」:103.1%
- 住友生命「こどもすくすく保険」:102.9%
参考:返戻率が高いおすすめ学資保険ランキング【2024年更新】 | アセットマネー
などがあり、「はじめのかんぽ」は返戻率で見るとやや控えめということがわかります。
返戻率は「数字だけを見ればわかりやすい判断材料」ですが、実は契約者や子どもの年齢、性別、払込期間、祝金の有無、支払い方法などでも変わってきます。
大切なのは、「返戻率の高さ=お得」と単純に考えるのではなく、自分たちの家計や目的に合っているかどうかをしっかり見極めること。学資保険を選ぶ際には、「いくら戻るか」だけでなく、「どんなときに安心できるか」「生活に合っているか」も含めて総合的に判断することが大切です。
かんぽ生命学資保険を途中解約すると返戻金はある?


結論からお伝えすると、かんぽ生命の学資保険を途中で解約した場合でも返戻金はあります。
ただし、その金額はタイミングや契約内容によって大きく変わり、「思っていたよりも少なかった…」というケースも少なくありません。
途中解約にはいくつかの注意点があります。とくに以下のような点に気をつけましょう。
- 契約初期(加入から数年以内)での解約:支払った保険料より返戻金の方が少なくなる「元本割れ」になる可能性が高いです。
- 事務コストや保障にかかる費用:費用が差し引かれているため、返戻金がごくわずか、あるいはゼロになることもあります。
- 保険料を払い終えていない途中の解約:返戻金が満期の受取金額より大きく下がるため、「損をした」と感じる方も多いです。
- 途中解約により保障がすべて消失:たとえば、契約者に万が一のことがあったとき、以後の保険料が免除される制度なども使えなくなります。
このように、途中解約には金額面だけでなく、将来的な保障の喪失という見えにくいリスクもあります。焦らず冷静に、「今すぐ必要な資金か?」「他に補える手段はあるか?」を考えて判断するようにしましょう。
かんぽ生命学資保険の元本割れはいつからする?


結論からお伝えすると、かんぽ生命の学資保険では、契約内容やタイミングによって元本割れが生じる可能性があります。とくに「返戻率が100%未満のプラン」や「契約してすぐの途中解約」の場合は、支払った保険料よりも戻ってくるお金が少なくなってしまいます。
元本割れが起きる主なケース
以下のような場合に、元本割れが起こりやすくなります:
- 返戻率が100%を下回っている契約の場合
→ 満期まで続けても、支払った金額より受け取る額のほうが少なくなります。
30歳男性が契約者・0歳児を対象に、全期間払込み・18歳満期・祝金なしのプラン。
・返戻率98.5%
- 契約初期に途中解約した場合
→ 解約返戻金が非常に少なく、元本割れはほぼ確実。
数年以内の解約では、返戻金がゼロまたはごくわずかになることもあります。
元本割れを防ぐためのポイント
元本割れをできるだけ避けるためには、次の点に注意しましょう。
- 契約前に返戻率をチェックする
→ 少なくとも100%を超えているかを確認。 - 払込期間を短くする
→ 10歳払込済など、期間が短いほど返戻率が高くなる傾向。 - 特約をつけすぎない
→ 医療保障などを追加すると、その分保険料が高くなり返戻率が下がることも。 - 途中解約を避ける
→ 特に加入してすぐの解約は損失が大きいので、よほどの理由がない限り避けた方が無難。
「お得なはずの保険なのに、損をすることもあるの?」と驚くかもしれませんが、学資保険は“安心”と引き換えに“運用効率”が抑えられている商品です。だからこそ、契約内容や家計の状況をよく確認し、「今の自分に合っているか」の見直しが大切です。
かんぽ生命の学資保険の解約のタイミングは?


結論から言うと、学資保険を解約するなら「できるだけ元本割れのリスクが少ないタイミング」で行うのがベストです。とはいえ、家計や生活状況によって、「今すぐ解約したい」と思うタイミングもあると思いますよね。
そこで、解約を検討する上で「損しにくい時期」と「注意すべきタイミング」について知っておくことが大切です。
解約するタイミングの判断ポイント
以下のような場合は、比較的「損をしにくい解約タイミング」と考えられます
- 保険料の払込が完了している場合
→ 払込完了後の解約は、元本割れのリスクが比較的低く、返戻率も高くなっていることが多いです。 - 満期まで残り数年で、今すぐに教育資金が不要な場合
→ 少し我慢すれば満額受け取れるタイミングなので、無理に解約するよりも満期まで持ち続ける方が得策です。 - 生活や家計に大きな変化があり、解約せざるを得ない場合
→ たとえば、医療費の発生や転職・離婚など。損失覚悟でも資金が必要なら、早めの解約もやむを得ません。
解約で損しやすいタイミングとは?
以下の時期に解約すると、返戻金が少なくなりやすく注意が必要です。
- 契約から3〜5年以内の「保険料をまだ払っている途中」の時期
→ 初期の解約では、手数料や保障コストが差し引かれるため、元本割れのリスクが非常に高いです。 - 特約や保障を残しておきたい事情がある場合
→ 解約によって「万が一の備え」や「医療保障」なども同時に失われてしまいます。
迷ったときの考え方
「いつ解約すべきか迷っている」という方は、まずは以下のように考えてみてください。
- 「満期まで続けられそうか?」
- 「今すぐ大きな出費が必要なのか?」
- 「返戻金と損益のバランスはどうか?」
- 「他に資金を確保する方法はあるか?」
これらを整理したうえで、必要であれば返戻金のシミュレーションを行い、「今解約するといくら戻ってくるか?」を確認してから判断するのが安心です。焦って行動するよりも、家計と気持ちに余裕を持ったタイミングでの見直しが、いちばんの節約と安心につながります。
解約は“損か得か”だけではなく、“今と未来、どちらを守るか”という選択でもあります。自分たちにとってベストな判断ができるように、一度立ち止まって考えてみましょう。
かんぽ生命の学資保険の解約返戻金はシミュレーションできる?


結論から言うと、かんぽ生命の学資保険は、自分で正確な返戻金額をシミュレーションすることはできません。現在のところ、ネット上で自由に使える「解約返戻金シミュレーター」のようなツールは、かんぽ生命の公式サイトには用意されていないのです。
そのため、返戻金の金額を正確に知りたい場合は、かんぽ生命の窓口や専用の問い合わせ先に確認する必要があります。
ただし、自分で大まかな目安を知る方法はあります。
自分で目安を確認するには?
- 契約書や保険証券を確認する
→ 契約時にもらった「契約内容のお知らせ」に、経過年数ごとの返戻金の目安が記載されていることがあります。 - お客さまWEBサービスにログインする
→ 登録済みの方であれば、かんぽ生命の「お客さまWEBサービス」で現在の返戻金を確認できる場合があります(ただし、すべての契約で対応しているとは限りません)。 - 契約内容と支払った保険料からおおよその返戻率を計算する
→ 「返戻率 =(受け取り総額 ÷ 払込保険料)×100」でざっくり計算できます。過去の契約内容の例を参考にすれば、おおよその位置づけがわかります。
残念ながら、保険料払込期間・特約の有無・契約経過年数などによって返戻金は大きく変動するため、完全に自分だけで算出するのは難しいのが現実です。
正確な金額を知りたい場合は、以下のいずれかの方法を使いましょう。
- 郵便局の窓口で相談(保険証券と本人確認書類を持参)
- かんぽ生命のコールセンター(0120-552-950)に電話
- 担当者による訪問相談(希望すれば対応可)
「自分で簡単に調べられたら助かるのに…」という声は多いですが、保険は個別設計が多いため、どうしても公式窓口での確認が確実です。
とはいえ、契約書のチェックやWEBサービスの利用で「だいたいこのくらいかな?」という見通しは立てられます。不安を減らす第一歩として、手元の資料やWEBログインを活用してみましょう。
かんぽ生命の学資保険に祝い金は付いている?


結論からお伝えすると、かんぽ生命の学資保険「はじめのかんぽ」には、契約内容によって“祝い金”が付くプランと付かないプランの両方があります。つまり、契約時にどちらを選んだかによって、祝い金があるかどうかが決まります。
「祝い金」とは、小学校・中学校・高校などの進学時にお祝いとしてもらえるお金のこと。 教育費がかかりはじめるタイミングで受け取れるため、「助かった」「ありがたい」と感じるパパママも多いです。
祝い金があるとどうなる?
祝い金が付いているプランでは、以下のような年齢の節目にお金を受け取れる場合があります。
- 小学校入学時(6歳)
- 中学校入学時(12歳)
- 高校入学時(15歳)
受取金額やタイミングは契約内容によって異なりますが、進学の節目にまとまったお金が入るのは、家計の負担が減るという点で安心感があります。
祝い金があると返戻率が下がることも…
一方で注意したいのは、祝い金を付けるとその分、返戻率(受け取れる総額の割合)が下がるという点です。つまり、「途中で小分けにお金がもらえる分、満期時にもらえる総額は少し減ってしまう」仕組みになっています。
そのため、「できるだけ高い返戻率を求めたい」「教育資金は大学進学時にまとめて必要」というご家庭では、祝い金なしのプランを選ぶケースも増えています。
自分の契約に祝い金があるかどうかを確認するには
- 保険証券や契約書の「保障内容」欄をチェックする
- かんぽ生命のマイページ(WEBサービス)にログインして確認する
- 郵便局やコールセンターで直接聞いてみる(0120-552-950)
「もらえると思ってたのに、ついてなかった…」というトラブルを防ぐためにも、今のうちに自分の契約内容をきちんと確認しておくのが安心です。進学のタイミングで「助かるお金」か、「返戻率を優先するか」それぞれの家庭の考え方やライフスタイルに合った選び方をすることが大切です。
かんぽ生命の学資保険は解約した方がいい?のまとめ


かんぽ生命の学資保険は、「解約した方がいい」と言われることもありますが、それがすべての人に当てはまるわけではありません。
大切なのは、今の自分たちの家計やライフプランに合っているかどうか。返戻率や返戻金、保障の内容などをしっかり確認したうえで、自分たちにとって納得できる選択をすることが一番です。
迷っている方は、一度現在の契約内容や返戻金を確認してみましょう。思い込みではなく、事実を見たうえで判断すれば、「これでよかった」と安心できるはずです。
要点まとめ
- 元本割れに注意が必要
- 解約はタイミングが大切
- 貯金で代用できる人も
- 安心感を重視する人もいる
- 解約前に返戻金を確認
「続けるのが正しい」も「やめるのが正解」も、誰かが決めるものではありません。あなたとご家族にとっての“ちょうどいい”を、じっくり選んでいきましょう。